
ベンチプレスと肩痛の関係性|原因から予防・改善まで徹底解説
こんにちは!
堺市堺区のパーソナルジムSAKURAのブログにようこそ!
今回はベンチプレスと肩痛の関係性についてお話ししています。
是非最後まで読んでコメントお願いします!
ベンチプレスは胸筋の発達を狙う代表的なトレーニングであり、筋トレ愛好者からアスリートまで幅広く取り入れられています。しかし、その一方で「ベンチプレスをすると肩が痛い」「トレーニング後に肩の違和感が強くなる」といった悩みを抱える人も少なくありません。特に中級者以上になると、重量が伸びていくにつれて肩関節への負担も大きくなり、怪我のリスクが増していきます。
本記事では、ベンチプレスと肩痛の関係性について、解剖学的・動作的な観点から掘り下げ、さらに予防法や改善法までを網羅的に解説していきます。
1. なぜベンチプレスで肩が痛くなるのか?
ベンチプレスは胸の大胸筋をメインターゲットにする種目ですが、実際には肩関節(肩甲上腕関節)と肩甲帯に大きなストレスがかかります。特に次の要因が肩痛を引き起こす主な原因となります。
1-1. 肩関節の構造的な弱点
肩関節は人体の中で最も可動域が広い関節です。その代償として、骨性の安定性が弱く、靭帯や筋肉(ローテーターカフ)に依存しています。ベンチプレスのように高重量を扱う動作では、この「安定性の弱さ」が負担増加につながりやすいのです。
1-2. 肩甲骨の動き不足
ベンチプレスでは肩甲骨をベンチに固定して行うため、自然な肩甲骨の可動性が制限されます。その結果、上腕骨の動きと肩甲骨のリズム(肩甲上腕リズム)が崩れ、インピンジメント(骨と腱がぶつかる現象)が起こりやすくなります。
1-3. 可動域とフォームの問題
バーを胸に深く下ろしすぎる(過度な肩関節伸展)
肘を張りすぎて90°以上に開いてしまう(肩の水平外転が大きすぎる)
これらは肩の前方構造(烏口突起周囲や前部関節包)に強いストレスを与え、炎症や痛みの原因となります。
1-4. 筋力バランスの崩れ
大胸筋や三角筋前部ばかりが強化され、肩の安定化に重要なローテーターカフや僧帽筋下部、前鋸筋などが弱いと、関節を正しい位置に保てなくなり痛みにつながります。
2. ベンチプレスと肩の代表的な怪我
肩痛を放置すると、慢性的な障害に進展することがあります。ベンチプレスと関連する代表的な肩の障害を整理しましょう。
2-1. インピンジメント症候群
肩を水平外転や外旋する際に、上腕骨頭と肩峰の間で腱板や滑液包が挟まれて炎症を起こす状態です。ベンチプレスで肘を張りすぎるフォームは典型的な誘因です。
2-2. 腱板損傷(ローテーターカフ損傷)
特に棘上筋腱が損傷しやすく、加齢や過度な負荷で部分断裂から進行します。ベンチプレス時の鋭い肩前方の痛みや、挙上困難が特徴です。
2-3. 関節唇損傷(SLAP損傷など)
重量を扱う中で肩関節の安定構造である関節唇が損傷すると、クリック音や引っかかり感、脱力感を伴う肩痛が起こります。
2-4. 上腕二頭筋長頭腱炎
肩の前方で炎症が起こり、ベンチプレス時にズキッとした痛みを感じるケース。腱板や関節唇損傷と併発することもあります。
3. 肩痛を引き起こしやすいフォームの特徴
・グリップ幅が広すぎる
肩の水平外転角度が大きくなり、関節に負担が集中します。
・バーを下ろす位置が鎖骨寄り
肩のインピンジメントを助長します。理想は乳頭ライン付近。
・肩甲骨の固定が不十分
ベンチ上で肩が浮くと、肩前方に過剰なストレスがかかります。
・柔軟性不足
胸椎伸展や肩関節外旋可動域が足りないと、無理なフォームになりやすいです。
4. 肩痛予防のためのチェックポイント
4-1. 正しいフォーム
肘は体幹に対して45°程度の角度を目安にする
バーは乳頭ラインに下ろす
肩甲骨を寄せて下制(下に引く)し、胸を張る
4-2. 適切な可動域
バーを胸に完全に付けなくても良い場合があります。肩が無理なく安定している範囲で可動域を設定しましょう。
4-3. ウォームアップ
いきなり高重量に入らず、チューブを使ったローテーターカフの活性化や、肩甲骨のモビリティドリルを取り入れることが重要です。
4-4. アクセサリーエクササイズ
フェイスプル(僧帽筋下部・後部三角筋強化)
エクスターナルローテーション(外旋筋群強化)
プッシュアッププラス(前鋸筋活性化)
これらはベンチプレスの安定性を高め、肩痛予防に直結します。
5. 肩痛が出たときの対処法
5-1. トレーニングの一時中断
痛みを無視して継続すると慢性化するため、まずは安静にして回復を優先します。
5-2. フォームの見直し
動画を撮影してセルフチェックしたり、トレーナーに確認してもらうことが有効です。
5-3. 医療機関での診断
鋭い痛みや夜間痛が続く場合は整形外科を受診し、画像検査(MRIなど)を行うことを推奨します。
5-4. リハビリエクササイズ
ペンデュラム運動(痛みを伴わない範囲で肩を小さく振る)
チューブ外旋運動(軽負荷でローテーターカフを刺激)
肩甲骨内転・下制運動(肩甲骨の安定化)
段階的に負荷を戻しながら回復を図るのが基本です。
6. ベンチプレスと肩の関係を良好に保つために
ベンチプレスは大胸筋の発達に優れた種目ですが、肩の構造的な弱点を考慮すると「正しい知識と準備」が欠かせません。肩痛を予防・改善するためには、
・正しいフォームの徹底
・肩甲骨とローテーターカフの強化
・柔軟性・可動域の確保
・無理のない重量設定
この4点を意識することが何より大切です。
特に「強い胸を作るには強い肩が必要」という視点を持ち、肩の安定性と健康を第一に考えることが、長期的にベンチプレスを楽しむための秘訣となります。
まとめ
ベンチプレスと肩痛の関係性をまとめると、まず理解しておくべきは肩関節の構造的な特徴です。肩は人体の中で最も自由度の高い関節である一方、骨による安定性が弱く、靭帯や腱、周囲の筋肉に強く依存しています。そのため高重量を扱うベンチプレスでは安定性の不足が露呈しやすく、肩への負担が大きくなります。特に肩甲骨をベンチに固定した状態では自然な動きが制限され、上腕骨と肩甲骨の協調リズムが乱れやすくなり、結果としてインピンジメントや腱板損傷といった障害につながります。フォームの乱れも肩痛の大きな要因であり、バーを胸に深く下ろしすぎることや肘を過度に張ることは肩の前方構造に大きなストレスを生じさせます。さらに大胸筋や三角筋前部に偏ったトレーニングを繰り返し、肩の安定性を支えるローテーターカフや前鋸筋、僧帽筋下部の働きが不十分である場合も関節にかかる負担は増します。実際に起こりやすい障害としてはインピンジメント症候群、腱板損傷、関節唇損傷、上腕二頭筋長頭腱炎などがあり、いずれも痛みや動作制限を伴いトレーニングを妨げます。肩痛を防ぐためには、肩甲骨をしっかり固定しながらも自然な動きを妨げないフォームを心がけ、バーを下ろす位置や肘の角度を適切に保つことが重要です。またローテーターカフや肩甲骨周囲筋を補強するエクササイズ、十分なウォームアップ、胸椎や肩関節の柔軟性向上も欠かせません。もし痛みが出た場合にはトレーニングを一時的に控え、フォームや可動域を見直すと同時に必要に応じて医療機関を受診し、段階的にリハビリエクササイズを取り入れていくことが望ましいです。ベンチプレスで胸を強くするには、同時に肩を守る意識が欠かせず、長期的にトレーニングを続けるためには「壊れない肩を育てる」という視点を常に持つことが鍵となります。
パーソナルジムSAKURAではお客様の体や食生活に合わせた食事指導を行なっております、大阪府堺市堺区でダイエットやボディメイクにお困りでパーソナルジムをお探しの方はぜひ一度体験パーソナルトレーニングなどご相談くださいませ!










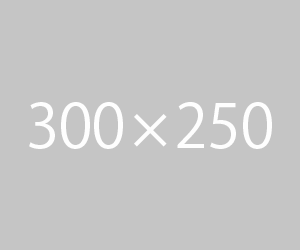
この記事へのコメントはありません。